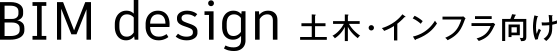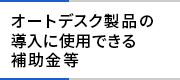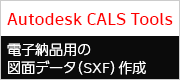ユーザー事例




【BIM/CIM原則化、改革者たちのメッセージ】
2023年度から国土交通省のBIM/CIM原則適用がスタートした。日刊建設通信新聞社がBIM/CIM原則化に向けて邁進する各分野のキーマンを取り上げたシリーズ連載『BIM/CIM改革者たち』から、建設業界が進むべき方向性を浮き彫りにする。記事は建設通信新聞からの転載。
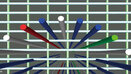
株式会社不動テトラ
BIM/CIMは施工管理業務の一環 現場主導で全面展開へ
不動テトラが国土交通省の BIM/CIM 原則適用に呼応するように、BIM/CIM の活用方針を「現場主導」に切り替えた。土木事業本部技術部設計課に所属する小林純 CIM/ICT プロジェクトチーム座長は「最前線を担う工事部が主体的になることで、現場目線の BIM/CIM 活用を拡大し、現場のデジタル化をけん引していく」と語る。目線の先には、国交省が掲げる i-Construction 2.0 への対応がある。同社の歩みに追った。

オリエンタルコンサルタンツ
DX手段に主導型ビジネスへ転換 BIM/CIMを高度活用
オリエンタルコンサルタンツの BIM/CIM 活用が DX(デジタルトランスフォーメーション)の領域に踏み込んでいる。DX 推進本部長の青木滋取締役執行役員は「業務プロセスの変革に向けた基幹技術として BIM/CIM が定着し、社を挙げた DX 推進へと深化している」と強調する。BIM/CIM の高度化により、建設コンサルタントとしての新たな役割も見え始めてきた。

NiX JAPAN
発注者から評価されるツールに成長
業務成績アップの効果鮮明に
7 月 1 日に社名変更した総合建設コンサルタントの NiX JAPAN(富山市、旧新日本コンサルタント)が、BIM/CIM を効果的に活用し、業務成績の評価点アップにつなげている。2021 年度に埼玉県発注業務の最高点を獲得、22 年度は水資源機構や東京都から優良表彰を受けた。BIM/CIM 推進室長を務める升方祐輔空間情報部部長は「発注者から評価されるツールとして BIM/CIM を使いこなしていく」と手応えを口にする。

ビッグ測量設計
点群にモデル統合の流れ拡大
工事測量の付加価値として 3 次元計測
国土交通省の BIM/CIM 原則化を背景に、建設コンサルタントや建設会社の 3 次元データ活用が広がりを見せる中、工事測量分野にも BIM/CIM 活用の流れが急速に広がり始めた。関東地区で鉄道や空港の関連工事を中心に活動するビッグ測量設計(東京都台東区)は、業界に先駆けて 20 数年前に導入した 3 次元レーザー計測技術を駆使し、工事測量や設計支援の有効な手段として BIM/CIM を活用するトップランナーの 1 つだ。

中央復建コンサルタンツ
将来の事業創出に向け「未来社会」描く ICT 戦略など 7 室が始動
建設コンサルタント業界の中でも先行して BIM/CIM に取り組んできた中央復建コンサルタンツが、BIM/CIM データを「賢く使う」ことで、新たな業務領域を切り開こうとしている。将来の活動領域として「未来社会」分野を定め、それを実現するための基盤ツールに ICT 活用を位置付ける。BIM/CIM を出発点にインフラ DX(デジタルトランスフォーメーション)の領域に踏み込む同社の成長戦略を追った。

日本工営
BIM/CIM 活用の新たなステージへ向けて 3次元自動設計への転換
国土交通省の BIM/CIM 原則化を機に、建設コンサルタントが 3 次元設計への転換を図り、BIM/CIM 活用の新たなステージに踏み込む動きが現れ始めた。BIM/CIM のトップランナーとして業界を先導する日本工営は自動設計システムを開発し、業務の効率化や高度化を実現しようとかじを切った。一歩先をいく同社の BIM/CIM 活用はどこに向かおうとしているか。

清水建設が配筋施工図の 3 次元モデルを自動作成! 現場ニーズ踏まえ、Revit で汎用ツールを開発
清水建設が、土木分野で基本設計図から配筋施工図の 3 次元モデルを自動生成するツールの開発に取り組んでいる。従来、現場担当の手書きによる配筋施工図の作成指示をパラメータ化し、モデリングソフトを介してオートデスクの BIM ソフト「Revit」から 3 次元の配筋施工モデルを作成する。「現場のニーズを的確に把握し、汎用性のあるツールとして仕上げていきたい」と語る同社土木技術本部イノベーション推進部先端技術グループの宮岡香苗氏と、プログラム開発を担う GEL(東京都江東区)代表取締役の石津優子氏に自動化ツールの方向性を聞いた。

東京コンサルタンツがBIM/CIMクラウド「Autodesk Docs」を200本導入!「容量無制限」と「ボリュームライセンス」でNASから乗り換え
BIM/CIMの本格導入に伴い、年々、増大する設計データの共有手段に頭を悩ませてきた東京コンサルタンツ(本社:東京都千代田区)は、2022年8月にオートデスクの建設向けクラウド「Autodesk Docs」(以下、Docs)のライセンス200本を導入し、全社で活用を始めた。決め手となったのは「容量無制限」と、NAS(ネットワーク接続型ハードディスク)の運用コストと比べても安価な「ボリュームライセンス」、セキュアな環境のもとでの「社内外からのスムーズなデータアクセス」だった。

配筋の構造細目に対する照査を自動化し、ロス率最小化を目指す! 清水建設が Revit などで配筋施工図の自動作成システムを開発
清水建設はオートデスクの BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフト 「Revit」を中心に様々なツールを活用し、配筋施工図を自動作成する システム(以下、配筋施工図自動作成システム)を開発した。配筋施工図を自動作成するためには、構造細目の照査等が欠かせず、これを自動化するため、様々なプログラム群を開発した。その結果、施工可能な配筋施工図を効率的に作成、設計変更にもスピーディーに対応できるようになる。さらに定尺鉄筋から最適に設計寸法に応じた「材取り」する機能によって、鉄筋ロス率も最小化できる見込みだ。

2000本の地盤改良杭の属性情報をRevitモデルに"一気に登録"! 不動テトラがDynamoでBIM/CIMによる施工管理
不動テトラは、オートデスクのビジュアルプログラミング言語ツール「Dynamo」を使って、BIM/CIMソフト「Revit」のモデルに属性情報を一斉に付与する「属性情報自動一括付与プログラム(仮)」を開発した。同様の機能を持つプログラムは、NavisworksやCivil 3D用には開発されていたが、Revit用としては初めてだ。不動テトラはこのプログラムを2000本に上る地盤改良杭の施工管理に使用したほか、今後、様々な工種の設計や施工管理に使用していく方針だ。

土木と建築が協力し、BIM/CIMモデルと点群を一体化! 岩田地崎建設の"デジタルツイン"施工管理
岩田地崎建設(本社:札幌市中央区)は、札幌市内に建設した地下駐輪場の施工管理で、オートデスクのBIM/CIMソフト「Revit」や「Civil 3D」などを活用。さらにBIM/CIMモデルを3Dレーザースキャナーで計測した街並みの点群データと合体させて、埋設管や歩道、そして近隣ビルまでを"デジタルツイン化"した。社内の土木・建築部門が協力し、地下から地上まで整合性がとれた施工計画で合意形成が早まり、工事の生産性向上を実現した。

清水建設が "現場に行かない"施工管理を実現、i-Construction大賞に! クラウドでBIMや点群、360°写真をリアルタイム共有
相模鉄道と東急東横線をつなぐ新線建設に伴い、JR新横浜駅の北側で巨大な地下駅の建設が進んでいる。施工を担当する清水建設は、オートデスクのクラウドサービス「BIM 360Docs」上で構造物のBIMモデルや、現場の点群データ、360°写真などを共有して"現場に行かない施工管理"が行えるようにした。これらのデータはVRやARでも活用。一連の取り組みは、2021年度の国土交通省「i-Construction大賞」を受賞した。


花田設計事務所が実現するプラント業界のデジタル化とビジネスの持続可能性
プラント設計の受託開発に専念してきた花田設計事務所が、その事業内容を3D設計へシフトし、大幅な効率化を実現。先進的な取り組みで築き上げたソリューションとアジャイルな事業展開により、その顧客へさまざまなメリットを提供しています。

【建設通信新聞 BIM/CIM未来図掲載】
建設コンサルはいま~ウエスコ事例
国土交通省の BIM/CIM 原則化を背景に、建設コンサルタント各社が 3 次元対応力の強化に舵を切り始めた。従来進めてきた業務のあり方を見直すだけでなく、組織としても新たな方向性を模索する動きに発展している。西日本を中心に活動するウエスコ(岡山市)もその 1 つだ。 岩元浩二執行役員技術推進本部長は「着実に人材を育てていくことが近道」と焦点を絞り込む。動き出した建設コンサルタント分野の今を追った。

建設コンサルタントの課題はデジタル技術で解決するしかない! 大日コンサルタントのDXを支えるBIM/CIM自動化戦略
建設コンサルタント業界には、生産年齢人口の減少や国土強靭化による業務量の増加、そしてベテラン技術者の退職など、多くの課題がある。そこで大日コンサルタントは、デジタル技術を全方位的に活用してこれらの課題を解決する DX(デジタル・トランスフォーメーション)戦略を掲げ、全社で取り組んでいる。その DX 戦略の実現のため、オートデスクの BIM/CIM ソフトを活用し、業務の迅速化や自動化を進めている。
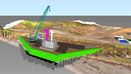
「BIM/CIMは絶対に外注してはならない」! 植木組が楽しむ"建設DXへの道"
新潟県柏崎市に本社を置く植木組は2016年に土木技術部の3人で、BIM/CIM活用を始めた。以来、実務での4DシミュレーションやMR(複合現実)など、実務での積極的な活用を進めている。「BIM/CIMの内製化」にこだわりながら生産性向上に挑戦する同社の技術者は、建設DX(デジタルトランスフォーメーション)への道を楽しんでいるかのようだ。

現場経験40年の技術者が、50歳からCivil 3Dを始めた!
シニアパワーがBIM/CIM活用を引っ張る玉川組
2018年にBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)/CIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)の本格活用を始めた玉川組(本社:北海道恵庭市)は、ベテラン社員が中心となってオートデスクのCivil 3DやRevit、InfraWorksなどのソフトを使いこなしている。その結果、プロジェクトの合意形成やICT土工などで生産性向上の効果が出始めた。シニアパワーがさく裂する同社のオフィスを直撃した。

若手社員がBIM/CIM活用をリードするアサヒコンサルタント
iPadによる点群計測や設計の自動化で急速に生産性を向上
鳥取市に本社を置く建設コンサルタント、アサヒコンサルタントはオートデスクのBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)、CIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)ソリューションを導入した結果、若手社員も難しい設計業務をこなし、作業スピードも大幅に向上させた。そのきっかけはRevitやCivil 3Dなどを使いこなす学生アルバイトの入社だった。
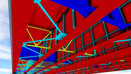
効率化と付加価値アップによる"攻めの生産性向上"
キタックが目指すBIM/CIM働き方改革
新潟市中央区に本社を置く建設コンサルタント、キタックではBIM/CIMを武器に生産性向上と働き方改革の両立を目指す「キタックBIM/CIM」戦略を推進している。2017年に初めてオートデスクの「AECコレクション」を2本導入した後、着々と社内で業務への活用を進め、現在では50本に。その特徴は、業務の効率化とともに、新サービスによる付加価値アップも目指す"攻めの生産性向上"にあった。

東急建設の渋谷 UiM が支援する東京メトロ銀座線渋谷駅の移設工事
東京都心の主要な繁華街、ビジネス街を網羅するように走る東京メトロ銀座線。現在は 1 日平均 100 万人以上の輸送が行なわれ、2017 年末に上野、浅草駅間が開通 90 周年を迎えたこの歴史ある地下鉄の、大規模なリニューアル工事が進められている。

"超精密"な薬液注入工事で CIM モデルを活用
東急建設が「Point Layout」を測量機器と連携し、作業量を従来の1/4に圧縮
東京・渋谷駅付近で、東急建設は古い橋台を撤去するため、周辺地盤への薬液注入 工事を行った。斜め下方に向かってボーリングし、地下にあるトンネルや建物の基礎などを傷つけず、橋台周囲の限られた地盤だけを改良するという "超精密"な工事を可能にしたのは、オートデスクの CIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング) ソフトと、トプコンの測量機を連携させるタブレット用アプリ「Point Layout」だった。

「技術者自身が3D設計しなければ、アイデアは生まれない」八千代エンジニヤリングが BIM/CIM に取り組む5つの理由
八千代エンジニヤリングは、国土交通省が推進する「i-Construction」施策よりも早く、2005 年度にオートデスクの土木用 3 次元 CAD「AutoCAD Land Development Desktop」(当時)を導入し、3D 設計を始めた。現在では約 800 人の技術者の 4 割に当たる 380 ライセンスもの BIM/CIM ソリューション「AEC Collection」を導入し、様々な分野の技術者が自ら、3D 設計に取り組んでいる。同社代表取締役社長 執行役員の出水重光氏に「BIM/CIM に取り組む 5 つの理由」を直撃取材した。

河川と道路が並ぶ景観エリアを CIM モデル化
大分・川原建設がCivil 3Dを選んだ理由とは
大分県中津市の川原建設は、名勝地・耶馬溪を通る国道 212 号が、自然景観に配慮した山国川の石積護岸と併走する護岸や樋門構造物を、オートデスクの「AutoCAD Civil 3D」で精密に CIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)モデル化、発注者との設計変更の協議や住民説明会のほか、現場での職人との打ち合わせや出来形管理、さらには広報活動まで幅広く活用した。

エイト日本技術開発、わずか1年でCIMを本格導入
設計段階での生産性向上を目指す
エイト日本技術開発(本社:東京都中野区)は、2016 年 9 月に CIM (コンストラクション・ インフォメーション・モデリング)の本格導入を目指す「CIM 推進委員会」を設置後、わずか 1 年たらずで 4 件のパイロットプロジェクトを実施した。今年度は専属の部署「CIM 推進室」を設置し、また東北から九州までの支社を交えた「CIM 推進委員会」 を立ち上げ、それらの成果をオートデスクが主催する「Autodesk University Japan 2017」で成果を発表するまでになった。短期間で CIM の全社導入に道筋をつけた秘密を取材した。

2,000 キロにわたる 高速道路の建設、維持管理を効率化
NEXCO 中日本の CIM 導入戦略
中日本高速道路(以下、NEXCO 中日本)は、2017 年に CIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)導入に着手し、既に中央自動車道小仏トンネルの渋滞対策事業や 新東名高速道路の土工工事などに導入している。今後、ICT 土工を本格的に採用 するほか、プレキャスト部材による橋梁工事の効率化や 2,000 km にもわたる高速 道路網の IoT(モノのインターネット)的な維持管理など、CIM による高速道路の建設、維持管理の生産性を大きく変えていきそうだ。

VR で橋脚補強の新工法を PR
第一建設工業の CIM 活用術
第一建設工業(本社:新潟市中央区)は、河川内での橋脚補強工事に欠かせない作業空間を確保する新しい仮設工法「D-flip 工法」を開発した。同社はこの工法の施工手順などをオートデスクの CIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)ソフトで 3D モデル化し、作業員への説明やウェブサイトでの PR に活用した。さらに VR(バーチャルリアリティー)化して、よりリアルなプレゼンテーションにも挑戦している。

i-Construction 時代の情報化施工に挑む 日本国土開発
AI を活用した未来の土工現場とは
重機を使った土工を強みとしてきた日本国土開発は、国土交通省の「i-Construction」政策の推進をきっかけに、ICT(情報通信技術)建機やドローンを駆使した情報化施工の技術開発に取り組んでいる。設計・施工の中心となるツールは、オートデスクのCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)用ソリューションだ。同社で CIM に取り組む技術者に直撃取材した。
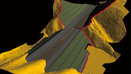
橋やトンネルから土工まで全国の約60現場に広がる大林組のCIM活用戦略を支えるソリューション
2012年2月にCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)の取り組みを始めた大林組は、3年弱で全国57カ所の現場に導入。オートデスクのCIMソフトウェアなどに、UAV(無人機)や3Dレーザースキャナー、3Dプリンターなどを組み合わせることによって、判断の迅速化や施工の効率化、維持管理モデルの構築などの成果を出している。

ドローンで渓谷を3D化、橋梁の景観検討に生かす
i-Constructionに挑む昭和土木設計(オートデスク)
昭和土木設計(岩手県矢巾町)は2013年、CIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)導入に取り組み始めた。その2年後には早くも、ドローン(無人機)やCIMソフトを活用した橋梁の景観検討で、「AUTODESK CREATIVE DESIGN AWARDS 2015 CIM部門」のグランプリを受賞した。同社は今、国土交通省のi-Construction戦略に対応して、CIMによる付加価値の高い設計業務を追求している。

渋谷駅駅周辺再開発の施工に威力を発揮 BIMとCIMを統合した東急建設の「UiM」
渋谷駅とその周辺でいま、大規模な再開発事業が行われている。その中でも 多くの工事を担当する東急建設はそれらプロジェクトの施工管理などに、同社独自の「UiM(アーバン・インフォメーション・モデリング)」というコンセプト/ワークフローを活用している。それをソフトウェアの面で支えるのは、オートデスクのBIM / CIMソリューションだ。

BIM / CIM による投資効果はいくらなのか? 設計者や実務者が定量的評価に挑戦
BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)や CIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)は、建設工事の品質、工程、コストなどを改善し、生産性向上に効果があると言われる。では投資効果はいくらなのか? この問題に BIM を活用する設計事務所や建設会社の実務者が、2日間取り組んだ。 200億円の建築プロジェクトを例に試算したところ、BIM による利益創出効果は工事費の 10% に及ぶものだった。

前田建設工業がCIM試行工事に Autodesk Revit、Civil 3Dを活用
トンネル施工の問題点を事前に解決
住宅地にはさまれた国道298号の地下に外かく環状道路のトンネルを構築する ―国土交通省の平成25年度CIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)試行工事で「希望型」に指定された工事で、前田建設工業はオートデスクのCIMソフト「Autodesk Revit Structure」、「AutoCAD Civil 3D」や「Autodesk Navisworks」を活用。施工上の問題点を施工計画の段階で発見し、解決する「フロントローディング」を実現した。

試行から実践へと進化
中央復建コンサルタンツのCIM活用
中央復建コンサルタンツは、価格競争に巻き込まれない差別化戦略の一環 として2007年にオートデスクの「AutoCAD Civil 3D」を30本導入し、3次元 設計への取り組みを始めた。翌2008年には早くも実務での成果を出して以来、現在までに100件以上の3次元設計やCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)プロジェクトを行ってきた。同社のCIM活用は試行から、全社での実践へと進化し始めた。