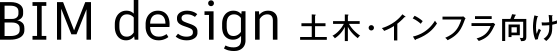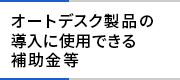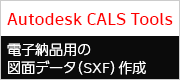株式会社 福山コンサルタント
「出遅れてしまう」思いが改革に 20 代中心に推進チーム発足
国土交通省の BIM/CIM 原則適用を背景に、3 次元データ活用に向ける受注者の意識が大きく変わり始めている。設計業務を担う建設コンサルタントでは先導役が将来を見据えて組織を新たなステージに導こうと奮闘する姿が目立つ。福山コンサルタントではインフラマネジメント事業部東京第 2 グループの栗山尚人係長が「このままでは出遅れてしまう」と意を決し、2 年半前に"改革"をスタートした。

2020 年 4 月に国交省が BIM/CIM 原則適用の開始時期を 25 年度から 23 年度に前倒したことを踏まえ、同社は研究開発リーディングプロジェクトとして BIM/CIM を位置付けた。社内では本社の道路設計チームが国交省直轄業務で BIM/CIM に取り組んできたが、全社的な広がりに発展しない状況があった。
リーディングプロジェクトのメンバーでもあった栗山氏が発起人となり、BIM/CIM 推進チームを立ち上げたのは 22 年 7 月のことだ。「いずれ BIM/CIM が一般化する。乗り遅れるわけにはいかない」。当時 20 代だった栗山氏はインフラマネジメント事業部長の門司雅道取締役からも背中を押され、「どこまでできるか不安はあったが、とことんやってみよう」と立ち上がった。
チームには本支店に置く道路と構造の設計部門から選抜した技術者 8 人と CAD オペレーター 7 人の計 15 人が参加した。20 代の若手を中心に組織したこともあり、BIM/CIM を理解していないメンバーも含まれていた。初年度から計 11 案件を試行業務として設定し、BIM/CIM にチャレンジすることを決め、「まず動いてみる」ことから始めた。
初年度に重視したのは BIM/CIM 業務を支える CAD オペレーターの育成だった。週の 1 日を BIM/CIM に取り組む日と定め、日頃の作図業務で使うオートデスクの汎用 CAD『AutoCAD』の 3 次元機能を習得してきたほか、土木設計ソフト『Civil 3D』やコンセプトデザインソフト『InfraWorks』などにも触れてきた。
栗山氏は「業務をやりながらのトレーニングになったため、毎週しっかりと時間をつくれた訳ではないが、オペレーターそれぞれが時間をやり繰りして主体的に取り組んでくれた」と振り返る。2 年目には技術者側も積極的に学んでいこうと、月に 10 時間のトレーニングを実施するとともに、インフラマネジメント事業部の約 100 人を対象にした希望参加による社内研修もスタートした。
実は、研究開発リーディングプロジェクトを発足した際にも BIM/CIM の社外研修には参加していたが、実務でチャレンジする機会が少なかったことから研修成果を生かせない反省があった。推進チームの活動目標として計 11 案件を位置付けたことで、選抜メンバーは日々の実務でしっかりと BIM/CIM と向き合ってきた。
東京第 1 グループの今里鈴花さんも、その 1 人だ。「メンバーに選ばれ、私自身の意識も大きく変わった」と語る。道路設計の協議資料には高低差など 3 次元での説明が有効な業務で BIM/CIM の可視化効果を積極的に活用している。「まだ高度な BIM/CIM 活用はできていないが、担当業務では常に有効な活用方法を考えるようになった」と付け加える。
BIM/CIM 推進チームの活動は 3 年目に入った。栗山氏は「チームの基盤は整い、次への一歩を踏み出す時期に入った」と決意をにじませる。何よりも BIM/CIM の下支え役である CAD オペレーターが「前向きに対応してくれたことが大きな推進力になっている」と強調する。
学ぶ意識が責任感とやりがいに/CAD オペが 3 次元けん引
福山コンサルタントの BIM/CIM 推進チームには、本支店からの技術者 8 人に加え、各グループから選抜された CAD オペレーター 7 人も参加した。同社は 2022 年 7 月のチーム発足時から CAD オペレーターの育成を活動方針の一つに掲げてきた。チームリーダーを務める栗山氏が「最初から 3 次元に対応できた人材もいた」と振り返るように、当初から CAD オペレーターが BIM/CIM の先導役として力を発揮してきた。
その 1 人、紫はるみさんはオートデスクの情報サイト『BIM design』に収録されている動画教材を使って以前から独学で BIM/CIM 関連ツールを習得してきた。社内研修用テキストも自作し、先生役として取り組んでいる。「AutoCAD の 3 次元機能をマスターするところから取り組み、徐々に他の BIM/CIM ツールにも挑戦していくことで無理なく学んでいける」とアドバイスしている。
渡邊加奈子さんも同社の BIM/CIM を支える CAD オペレーターの 1 人だ。活用するオートデスクの BIM/CIM ソフトは複数あり、モデリングに際して道路構造令などの技術的な知識も求められるだけに「BIM/CIM にチャレンジするようになって常に学ばないといけないという意識が芽生え、それが責任感ややりがいになっている」と強調する。
CAD オペレーターは BIM/CIM に取り組む中で、どう対応すればいいか、判断に苦しむ場面も少なくない。栗山氏は「実は、その相談役として外部のアドバイザーにも入ってもらった」と明かす。同社は建設 DX(デジタルトランスフォーメーション)のスタートアップ(新興企業)として豊富な実績を持つ ONESTRUCTION(鳥取市)や Malme(東京都千代田区)などと契約し、BIM/CIM ソフトのレクチャーに加え、最新技術や国内外のデジタル化の動向についても意見交換してきた。
「自社内でスキルを上げていくには限界があった。経験豊富な方から学ぶことで、より実践で有効なスキルを習得できる」。CAD オペレーターはトレーニングする中で、属性情報の扱いやソフトの高度な操作方法などを相談した。渡邊さんは「目的にあった BIM/CIM モデルづくりを丁寧に教えてもらえたことが、実務に生きている」と感謝している。
業務ではオートデスクの土木設計ツール『Civil 3D』を活用して道路設計の 3 次元モデルを作成し、そこから縦断図や横断図を出力するほか、統合モデルの作成ではコンセプトデザインソフト『InfraWorks』をフル活用している。「アドバイザーの方々が、経験に基づいたツール活用のコツを分かりやすく伝授してくれたことで、作業効率が向上している」と続ける。
栗山氏は、いずれ BIM/CIM 推進チームメンバーが各部門の推進役として活動することを期待している。「メンバーが BIM/CIM マネージャーとして機能すれば、組織としてもより機動的に BIM/CIM への対応力を増していける」と強調する。
同社は BIM/CIM 業務におけるモデリング作業のすべてを内製化することを基本にしているが、業務量に応じて簡易作業の一部を外部に委託することも考えており、今後を見据えて国内外の対応可能な協力会社との連携も模索している。国土交通省の BIM/CIM 原則適用がスタートしてまもなく 2 年が経過する中で「われわれも着実に対応力を引き上げている」としっかりと先を見据えている。
推進チーム軸に成功体験を蓄積/社会課題解決のツールに
福山コンサルタントの BIM/CIM 推進チームが発足して2年半が経過した。チームリーダーを務める栗山氏は「メンバーのモチベーションを引き上げることが私自身の役割でもある」と語る。
国土交通省の BIM/CIM 原則適用が動き出し、設計業務ではいずれ 3 次元設計の流れが進展してくる。「建設コンサルタントにとって BIM/CIM の対応は欠くことのできない重要なスキルであり、個としても組織としても知識レベルを引き上げていかなければいけない。われわれチームがコアとなり、着実に成功体験を積み上げていく」と思いを込める。
2024 年 3 月に設立 75 周年を迎えた同社は 100 年企業を目指す上で、企業価値の向上や社会貢献を実現するツールとして BIM/CIM を位置付けている。インフラマネジメント事業部長の門司雅道取締役は「これからも BIM/CIM を活用しながら社会課題の解決に挑戦し、ステークホルダーの期待を越える成果を導く」と強調する。
同社は、BIM/CIM の重要な役割として「社会課題の解決」「地域活性化への貢献」「独創的な事業展開」「視覚的支援と働き方改革の推進」の四つを掲げる。中でも「3 次元データを活用したシミュレーションやデータ分析による高精度な計画立案は、安全・安心のインフラ整備を目指す当社の使命と一致している」と説明する。
特に BIM/CIM 活用による見える化効果は「プロジェクト関係者間の情報共有を円滑化し、意志決定の迅速化やプロジェクトの透明性向上にも期待できる」と位置付けている。こうした考え方は、BIM/CIM 推進チームの"挑戦"という形で具現化されつつある。
社内ではオートデスクの BIM/CIM ツールを自由に利用できる AEC コレクションを従量課金制で購入している。強みの道路設計ではオートデスク製品と相性の良いビジュアライゼーションソフト『Twinmotion』をフル活用し、安全対策走行シミュレーションを作成した事例も出てきた。ゲームエンジン系の専用ソフトを活用せず、あえてオートデスク製品だけでリアルな走行空間を構築した。
栗山氏は「BIM/CIM データを発注者に対してどう見せていくか。それが有効な合意形成の手段になる。ビジュアライゼーションについては他の業務でも積極的に活用していきたい。3 次元都市モデルや点群データなどを使ったパースとしての活用も準備している」と説明する。
BIM/CIM は設計から施工、維持管理へとデータをつなぐことが理念にあり、設計業務単体では導入効果が限定的とも言われているが、調査や計画立案の段階では有効な判断材料として BIM/CIM データを活用できる。重要なのは「技術者としてモデルを使って何ができるかを考えることであり、それによって設計時に付与すべき情報やモデルの在り方についても最適解を導くことができる」と焦点を絞り込む。
今里さんは「メンバー全員に小まめに声を掛けてくれる」という栗山氏を通じて「私自身の BIM/CIM への向き合い方が大きく変わった」と受け止めている。3 年前に「このままでは乗り遅れる」と立ち上がった栗山氏の思いが、BIM/CIM 推進チーム発足のきっかけとなり、いまではその前向きな目線をメンバーがしっかりと受け継いでいる。チームの意識改革が同社の BIM/CIM 活用の流れを一気に速めようとしている。
この事例は2025年2月3日から2月5日までに日刊建設通信新聞で掲載された「連載・BIM/CIM未来図 福山コンサルタント」を再編集しています。